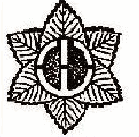学校沿革
小山小学校の開校の頃
小山小学校は、幾たびかくりかえされた市川(百々川)の氾 濫により形成された百々川扇状地の扇頂部分に位置し、名勝臥竜山のふもとに建設された。小山地 籍は、湧水もあり、臥竜山が、自然の堤防の役目を果たしたので、古来よりの集落地であった。南原の上で取水し、小山・屋部・八幡・境沢を通過し高梨方面に
流れ下る用水路は、人々の重要な飲料水、田の用水となっていた。昔の小山村は、この堰水を共にする村々の集合体であった。明治初期は、小山村、坂田村、大
日向村、灰野村と市川沿いの四箇村との結び付きが強く、小山村は、南原、穀町、北原、屋部、八幡、境沢、高梨の一部を含む大村であった。
濫により形成された百々川扇状地の扇頂部分に位置し、名勝臥竜山のふもとに建設された。小山地 籍は、湧水もあり、臥竜山が、自然の堤防の役目を果たしたので、古来よりの集落地であった。南原の上で取水し、小山・屋部・八幡・境沢を通過し高梨方面に
流れ下る用水路は、人々の重要な飲料水、田の用水となっていた。昔の小山村は、この堰水を共にする村々の集合体であった。明治初期は、小山村、坂田村、大
日向村、灰野村と市川沿いの四箇村との結び付きが強く、小山村は、南原、穀町、北原、屋部、八幡、境沢、高梨の一部を含む大村であった。
徳川時代、坂田村・小山村は、須坂藩に所属し交通路とし
て、北国街道、千曲川沿いの谷街道、江戸への裏街道としての大笹街道に近く、外部との交渉が盛んに行われ、住民の教育への意識も強かった。江戸末期頃か
ら、寺子屋や私塾が増加した。この普及と教育に対する願いが、明治六年小山小学校の前身となる「止善学校」開設へとつながる原動力となっていくのである。
幾多の変遷を経ていく中で多くの新しい教育実践が行われた。 止善文庫は、大正元年12月351冊の蔵書と経費40円をもって発足した。
その対象者は、青年子女であり、閲覧・貸出を行い多くの利用者があった。大正15年、止善文庫と他の本を合わせ、須坂町の図書館として開館。現在の須坂市立図書館の前身となっている。
合唱、図書教育、マラソン、環境教育
昭和30年から3年間、長野県教育委員会より音楽教育実験学校の指定を受け、いままでの積み重ねの上に立ち取り組み、「音楽の小山」と言われるようになった。昭和40年代には、テイームテイーチングを取り入れたり、視聴覚機器等の積極的な導入がなされた。
これらの向学の気風は、現在も学校に地域に伝統的に存在 し、学校への地域父母の方々の理解と協力となって現れている。3年前から始まった週休日を使っての図書館開放でのボランテイアとしての協力、スキー教室の 父母による指導などは、それである。また、大きな生徒指導上の問題も、長期的な不登校児童もいないこともそのあらわれとおもわれる。
ここ数年来、豊かな人間関係を作る為に異学年集団による様々な活動が組まれ、学年を越えて遊ぶ児童の姿がみられるようになってきている。
臥竜公園の一部ともいえる小山小学校は、臥竜山・臥竜公園を使っての多くの学習活動が組まれてきた。臥竜公園清掃、竜が池マラソン、自然観察、民話、写生等、臥竜公園を素材として多くの教育活動が組まれ、児童の心身を豊かに育んできた。
学校の校庭の片隅にある樹齢百年を越える「栃の木」は、本校のシンボルとなっており、教材化されたり、朝な夕な児童を見守り、心の糧となっている。
小山小学校の沿革(概要)
明治6年12月止善学校(小山村円光寺内)設立
「止善」とは:中国の古書「大学」に「在止於至善」という言葉があり、「至善に止まるに在る」からの命名で「この境地に達するには人の道を求めてやまず、人生の目的を見つけ理想に向かって一歩また一歩確実に歩み続けることを念願する」という意味です。


明治11年現位置に新築移転
明治15年 小山学校設立許可
明治19年4月 須坂学校小山支校
明治22年4月 小山尋常小学校
明治30年3月 小山尋常高等小学校
明治35年4月 小山尋常高等小学校
大正11年7月 須坂尋常高等小学校小山部校
昭和16年4月 小山国民学校
昭和22年4月 須坂町立小山小学校
昭和29年4月 須坂市立小山小学校
昭和48年開校100周年記念式典挙行
昭和53〜56年度の4カ年にわたり校舎、体育館、プール全面改築
小山の歴史
1879年明治12年1月14日郡区町村編制法に基づき、長野県高井郡を上高井郡と下高井郡に分割した事で発足。郡役所は須坂町に置かれた。
1889年(明治22年)4月1日 - 町村制施行に伴い、上高井郡に須坂町と14の村が成立する。(1町14村)
1892年(明治25年)1月29日 - 小山村が豊丘村に改称。
1922年(大正11年)7月1日 - 豊丘村小山・坂田地区が須坂町に合併。
詳しくは、Wikipedia上高井を参照。